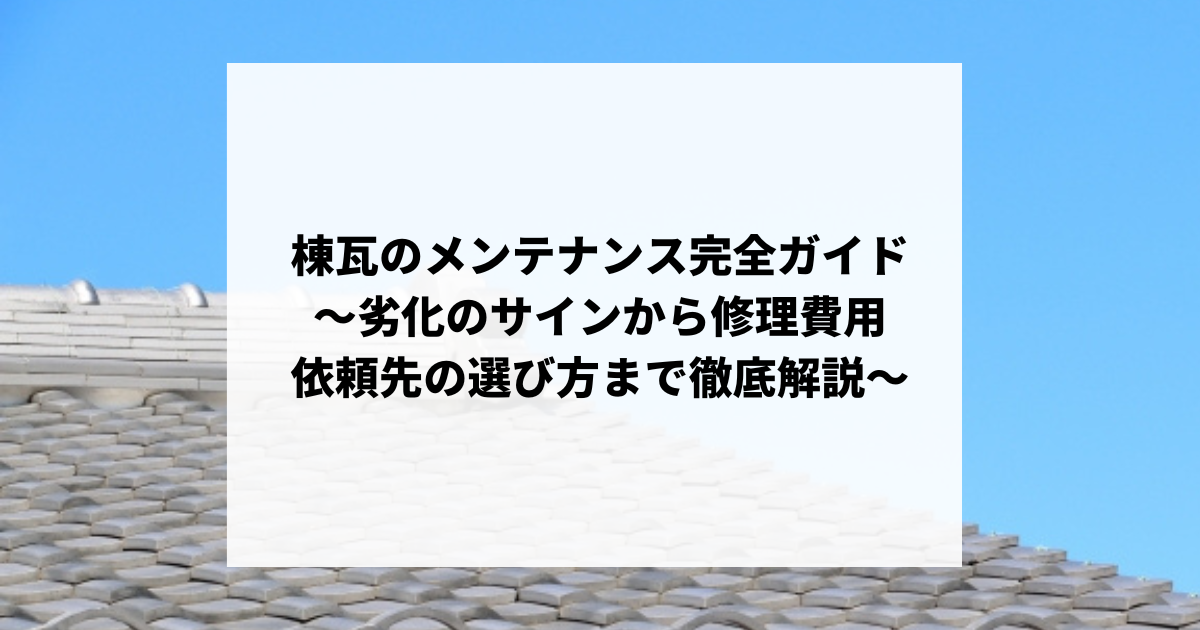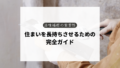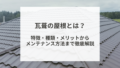1. はじめに
棟瓦(むねがわら)とは、屋根の最頂部に使用される瓦のことで、屋根と屋根の境目をカバーし、雨風の侵入を防ぐ重要な役割を担っています。日本は台風や地震が多く、屋根の負担が大きいため、棟瓦が劣化しやすい環境といえます。もし棟瓦が傷んだまま放置すると、雨漏りや建物内部の腐食など二次被害へと繋がる恐れがあるため、定期的なメンテナンスが欠かせません。本記事では、棟瓦の劣化サインやメンテナンス方法、修理費用の相場、依頼先選びのポイントを徹底解説します。
2. 棟瓦の構造と役割

棟瓦は、屋根の頂部(棟部分)を覆う瓦のことを指します。一般的な瓦屋根では、葺き土(ふきど)や漆喰(しっくい)が下地として用いられ、これらが棟瓦をしっかりと固定する役割を果たしています。
-
葺き土:瓦と瓦の隙間を埋め、下からの雨水浸入を防ぐ土。
-
漆喰:葺き土を覆い、風雨から保護すると同時に仕上げ材として美観を保つ。
こうした構造で、屋根全体の耐久性を高めています。しかし、棟瓦と漆喰、葺き土はいずれも経年劣化が起こりやすく、台風や地震などで大きく動かされると、瓦のズレや漆喰の剥がれが目立つようになります。また、同じ瓦屋根でも部材の品質や施工方法によりメンテナンス性が異なるため、定期的な点検で早期発見することが大切です。
3. 棟瓦の劣化サインと点検ポイント
棟瓦のメンテナンスを適切なタイミングで行うためには、下記の劣化サインを見逃さないことが重要です。
-
漆喰の剥がれ・ひび割れ
漆喰は葺き土の保護層として機能しますが、経年とともに剥がれやひび割れが起こります。小さな亀裂でも、そこから水が浸入する恐れがあるため要注意です。 -
瓦のズレや浮き
台風の強風や地震の揺れによって、棟瓦がズレたり浮き上がったりすることがあります。屋根の頂部が波打って見える場合は、何らかのズレが生じている可能性が高いです。 -
棟の歪み、波打ち
棟全体が歪んでいたり、段差ができていたりすると、内部の葺き土が流出している可能性があります。雨水の侵入リスクが高まるため、早期点検が必要です。 -
雨漏りや室内の異変
天井や壁にシミやカビが発生している場合、棟瓦からの雨水浸入が疑われます。室内の異常は屋根トラブルの最後のサインになりがちなので、早めの対策を行いましょう。
これらのサインを見つけたら、屋根全体の状態を専門家にチェックしてもらうのがおすすめです。高所作業は危険なうえ、誤った自己判断で対処すると棟瓦修理以外のトラブルも招きかねません。
4. メンテナンスを怠るリスク
棟瓦の劣化を放置すると、以下のようなリスクが高まります。
-
雨漏り・木部腐食・カビ発生
棟瓦や漆喰の破損から雨水が侵入し、柱や梁などの木部を腐食させる恐れがあります。また、湿気の多い環境はカビやシロアリの繁殖を促進し、建物の耐久性を著しく損ないます。 -
棟瓦の崩落による二次災害
台風や地震などの際、棟瓦が大きく崩落すると、下にいる人や周辺建物を直撃する可能性があります。人的被害や近隣トラブルの原因にもなり得るため注意が必要です。 -
屋根全体の構造ダメージと修繕費の増加
棟の不具合がほかの瓦や下地構造にも波及すると、部分修理では済まなくなるケースも。結果的に大掛かりなリフォームが必要となり、費用が大幅に増加する恐れがあります。
5. 棟瓦のメンテナンス方法と費用相場

棟瓦のメンテナンス方法には主に「詰め直し工事」と「棟取り直し工事」があります。それぞれ費用と工法が異なるため、状態に合わせて適切な施工を選びましょう。
5-1. 詰め直し工事
-
概要
漆喰や葺き土が一部剥がれている場合や、軽微なズレの場合に行います。傷んだ漆喰を取り除き、新しい漆喰と葺き土を充填し直して固定する工事です。 -
費用相場
1メートルあたり3,000~7,000円ほど。棟の長さや瓦の種類によって前後します。
5-2. 棟取り直し工事
-
概要
棟瓦自体が大きくズレていたり、葺き土が流出しているなど大規模なダメージの場合には、棟全体を一度取り外し、新たに積み直す工事が必要です。 -
費用相場
1メートルあたり8,000~15,000円程度。瓦の種類や屋根の形状によってはさらに変動します。
5-3. 足場設置費
工事内容に応じて足場の設置が必須となる場合があり、その費用は10万~25万円程度が目安です。屋根が高い、勾配が急など、危険性が高いほど足場費用は上がる傾向にあります。
5-4. 火災保険適用の可能性
台風や強風など「風災」による棟瓦の破損の場合、火災保険が適用されるケースがあります。加入している保険プランや被害状況によって異なるため、保険会社や業者に相談して確認しましょう。申請には被害状況の写真や修理見積書などの書類が必要になります。
6. DIYと業者依頼、どちらがベスト?
棟瓦の修理をDIYで行うケースもありますが、基本的にはプロに依頼するほうが安全かつ確実です。
-
DIYのリスク
高所作業は落下の危険が伴い、瓦を踏み割るリスクも高まります。また、仕上がりにムラがあると、再度雨漏りや棟瓦のズレが発生する恐れがあります。 -
プロに依頼するメリット
専門的な技術と知識により、耐久性の高い仕上がりが期待できます。施工後の保証やメンテナンスアフターなども利用できるのが魅力です。 -
業者選びのコツ
施工事例や口コミの評価をチェックし、地域密着型の業者を選ぶと安心です。とくに施工後のトラブル対応がスムーズな点がメリットでしょう。
➡︎ TEPPENリフォームの施工事例はこちら(内部リンクを想定)
7. メンテナンスのタイミングと頻度
棟瓦のメンテナンスは、一般的に10年を目安に点検を行うことが推奨されています。しかし、日本は台風・地震など自然災害のリスクが高いため、災害後は速やかに屋根の状態をチェックすることが重要です。早期に異常を発見すれば、小規模な修理ですむ可能性が高く、コストや工期を大幅に抑えられます。
定期点検を欠かさず、少しでも気になる症状があれば専門業者に相談してみましょう。
8. まとめ
棟瓦のメンテナンスを適切に行うことは、雨漏りや棟瓦の崩落などの重大なトラブルを未然に防ぎ、建物の寿命を伸ばすうえで非常に重要です。棟瓦が劣化している状態を放置すれば、将来的に大掛かりな修繕費用がかかるリスクも高まります。早めのメンテナンスと、信頼できる業者の選択がコスト削減と安心につながるポイントです。屋根の健康状態に不安がある方は、ぜひプロへ相談してみてください。